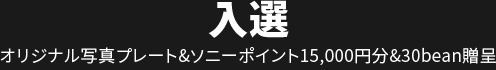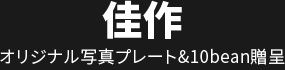![]()
この写真の主役は、昔ながらの路地に差し込む太陽の光。庶民の生活の場にも、明日の希望を運ぶがごとく夕日が差し込むわけです。猫もうまいところにいて、脇役として実に決まっている。茶色い色彩が多い中、ポストの赤が効いていますね。路地裏の、昭和の感じが残った空気感がものの見事に映し出されていていると思います。太陽が絶妙なところから差し込み、絶妙なところに猫がいたという、被写体との出会いとシャッターチャンスは写真の神様がくれたものでしょう。写真というのは、やはり光ですね。photoは「光の」、graphは「描くもの、描かれたもの」。「光で描く絵」がphotographなんです。この写真は光の妙味をよく捉えていますよね。こういう作品を見ると、光がいかにたいせつかということをあらためて感じます。
![]()
6人のお子さんがベンチに座ってかき氷を食べているというというほほえましい状況です。でも、子どもたちはかき氷ではなく視線の先にある「何か」に夢中になっている。6人もいると、誰かひとりくらいカメラのほうを意識したりしがちなんですが、みんな同じテンションにいる瞬間をうまく捕らえました。撮られていることを意識していない子どもたちの素顔、リアリティが表れていると思います。モノクロ化したことでドキュメンタリーっぽさも出ていますよね。テクニック的にはうまく逆光を使っています。逆光というのは、ものごとを立体的に浮き彫りにさせるんですが、そのことを上手に使っていて「写真を良く知っている人」という気がします。
![]()
秋の落ち葉が主役で、パースペクティブ(遠近感)を良く捉えています。非凡なアングルを得て葉の存在感が十分表現できていますし、浅い被写界深度で、うしろの橋の消失点まで映っていることで奥行きも出ました。少し黄色に被せた色調が、秋の気配・空気感を醸しています。構図、被写体とカメラとの距離感、低い位置からカメラを構えたアングル、この3つが勝因ですね。作者は「消えゆくものへの共感・寂しさ」をテーマにしていますよね。われわれは、一見、華やかで新しいものに注目したがりますけれども、終わりのせつなさやあわれというものが、十分に写真のテーマになり得ることを表現してくれたと思います。